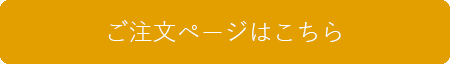激しい憤怒相と朱と金の彩色が映える、伝運慶作の愛染明王像。
源頼朝公ゆかりの高野山別格本山 金剛三昧院(こんごうさんまいん)の本尊が、TanaCOCORO[掌]に再登場です。
リクエストに応え、
再販決定!
北条政子が源頼朝公の菩提を弔うため発願した、または頼朝公が自身の等身大念持仏として造らせたと伝わる金剛三昧院の本尊 愛染明王像。その大胆かつ精緻な造型を手のひらサイズで細部まで忠実に再現しました。
2022年に200体限定でデビューするも早々に完売し、お問い合わせが絶えないことから、この度100体限定で再販いたします。
激しい憤怒相と朱と金の彩色が映える伝運慶作の像を、ぜひこの機会にお迎えください。
世界遺産・高野山の歴史を
色濃く残す
名刹 金剛三昧院
「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として世界遺産に登録された高野山で唯一、塔頭寺院*として登録される別格本山 金剛三昧院(こんごうさんまいいん)。
建暦元(1211)年、鎌倉幕府初代将軍 源頼朝公の菩提を弔うため尼将軍 北条政子が創建した「禅定院」を前身とし、数多の有力武将の帰依を受けて発展し、高野山における鎌倉幕府の出先機関として力を持った寺院です。
境内にある国宝の多宝塔は、貞応2(1223)年に建立された高野山に現存する最古の建立物であることから、現在は「高野山で唯一、国宝を所有する宿坊」としても人気を集めます。
*塔頭(たっちゅう)寺院…総本山の境内にある寺院のこと。
煩悩即菩提
欲望を悟りへと導く愛染明王
![TanaCOCORO[掌] 愛染明王](https://ssl.isumu.jp/img/tc3782/a1.jpg)
数ある煩悩の中で最も断ち難い愛欲を、悟りを求める心(菩提心)へと変えてくれる愛染明王。
様ざまな縁を結ぶことから、恋愛成就に限らず良縁や無病息災、戦勝といったご利益を願い、鎌倉時代以降、広く信仰されるようになりました。
全身を朱に染め、なんとしても人びとを救おうとする強い決意を憤怒の相で表し、悟りへの固い決意を示す五鈷鉤(ごここう=五つのカギ)をつけた獅子の冠を頭上に戴きます。
伝運慶作、迫力の造型
金剛三昧院本堂の中心に鎮座する本尊 愛染明王像は、源頼朝公逝去の際に妻 北条政子が運慶に依頼して造らせた、もしくは頼朝公が運慶に依頼して造らせた自身の等身大念持仏とも伝わります。寺院と鎌倉幕府との強いつながりや、当時東国に滞在していた運慶の影響の大きさを感じさせる像です。
永きにわたり信仰を受けた体躯の朱は全体的に剥落し、露出した黒褐色の身色が強い憤怒相に一層の迫力を与えます。悟りへの強い願いを示す火炎の円光背や細かな持物、台座の宝瓶をぐるりと囲む小さな宝珠に至るまで、大胆かつ緻密な造型が圧巻の存在感を放ちます。
細部へのこだわり

五鈷鉤をつけた獅子冠は、障害に打ち勝つ強さを象徴する。

激しい憤怒相。額には、あらゆる世界を見通す第三の眼を持つ。

腰までしなやかに伸びる頭飾は、破損のないよう真鍮で緻密に制作。

五鈷杵、五鈷鈴、弓矢などの細かな持物も細部まで丹念に再現。

智慧の詰まった宝瓶に咲く蓮華の上に結跏趺坐する独特のポーズ。

モデル像の光背を支える背面の支柱も造形の一つとして再現。
























イスムの技術を駆使してTanaCOCORO[掌] サイズにその魅力を凝縮。厳しさの中にも慈悲深さを感じさせる憤怒相、細かな持物、台座の装飾まで丁寧に造型し、手のひらサイズながらモデル像の持つ迫力や存在感そのままに仕上げました。
![TanaCOCORO[掌] 愛染明王](https://ssl.isumu.jp/img/tc3782/b1.jpg)
![TanaCOCORO[掌] 愛染明王](https://ssl.isumu.jp/img/tc3782/b2 .jpg)
![TanaCOCORO[掌] 愛染明王](https://ssl.isumu.jp/img/tc3782/b4.jpg)
![TanaCOCORO[掌] 愛染明王](https://ssl.isumu.jp/img/tc3782/b3.jpg)

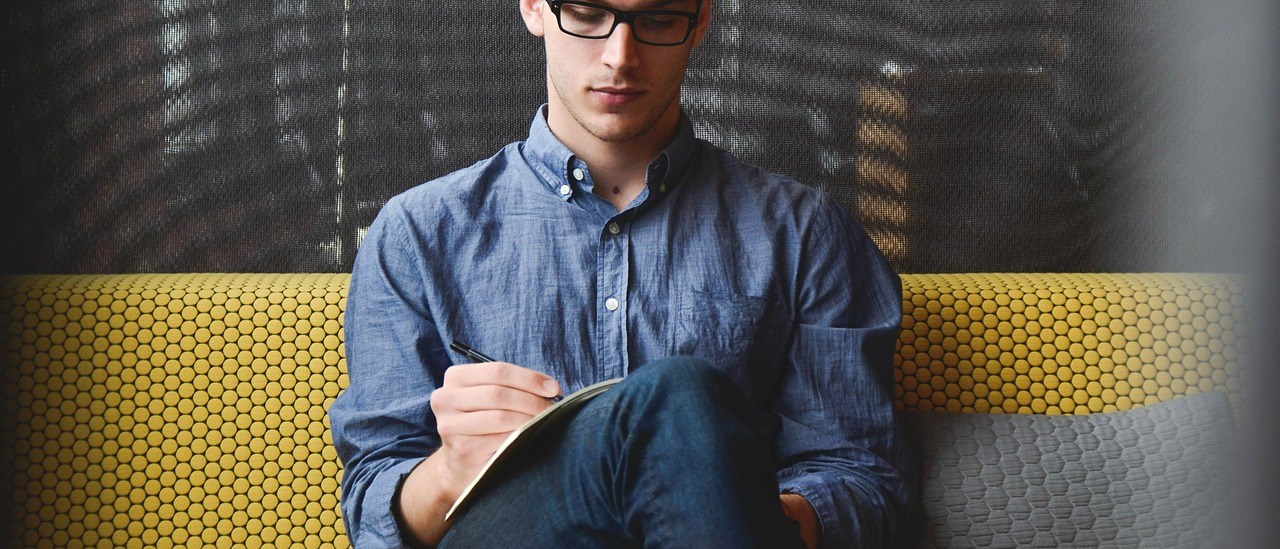
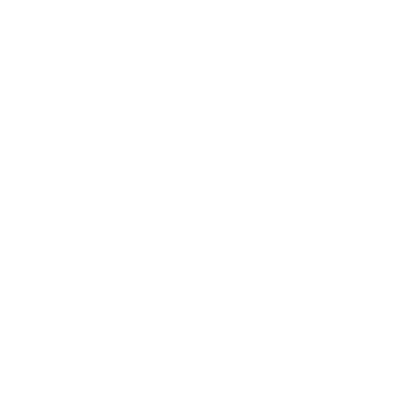

![TanaCOCORO[掌] 愛染明王](https://ssl.isumu.jp/img/tc3782/d1.jpg)
![TanaCOCORO[掌]](https://ssl.isumu.jp/img/tc3746/tc.png)